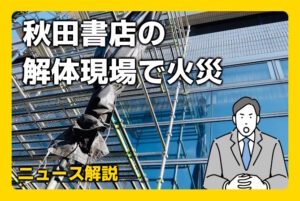解体工事の地中埋設物とは?撤去費用はどのくらい?
解体工事を行うと地中から予想外の物が出てくることがあります。これがいわゆる「地中埋設物」で、あらかじめ想定されていたものなら問題ありませんが、施主さんも想定外だった場合はその撤去をどうするかで検討が必要になってきます。
本記事では、そんな地中埋設物について、その種類やトラブル例、対応策、撤去費用について解説します。
地中埋設物とは?どんなものがある?
地中埋設物とは、建物の解体中もしくは解体後に地面の中から見つかる構造物や廃材のことです。以下のようなものがあります。
《主な地中埋設物の例》
- コンクリート基礎
- 地中梁・杭・ベタ基礎
- 浄化槽・便槽
- 井戸・地下水タンク
- ガラ(瓦礫やレンガ)
- アスファルト・残置配管
- 古い設備(ボイラー、焼却炉など)
- 土中の廃材や生活ゴミ(昔の建物の残骸)
基礎や杭の類、浄化槽などはあるのが分かっているので見積りにも工程に入れられていることが多いですが、昔埋めた井戸やガラの類になると施主さん自身も知らないか忘れているケースが珍しくありません。
地中埋設物でよくあるトラブル例
地中埋設物が原因で起きるトラブルには、以下のようなケースがあります。
追加工事費用が発生
解体工事でよくあるのが見積もり時にはわからなかったものの、解体工事中に埋設物が出てきたというケース。弊社では、事前に地中埋設物の可能性について言及し、もし、想定外の埋設物が出てきた場合は別途費用がかかりますと見積もり段階でお伝えしています。
工期の遅れ
少量、小規模な埋設物なら問題になることもありませんが、広範にわたって埋められているような場合は埋設物の撤去に時間がかかり、次の建築工事の開始に影響が出るケースもあります。
責任の所在で揉める
土地を売った後に埋設物があることが発覚した、工場跡地を購入したら土壌汚染が確認されたといったようなケースだと、売主と買主が責任の所在を争うケースがあります。
土壌汚染・産廃処分が必要
古い廃棄物が有害物扱いになることもあります。例えば鉛やヒ素などの重金属、灯油や軽油などの油汚染、その他農薬などは土壌汚染が疑われ、法律によってさらなる調査と対応が必要になってきます。
また、コンクリートガラや瓦などの廃材、汚泥などが出てきた場合は産業廃棄物として処理が必要になります。
地中埋設物の対応策
事前の調査・説明を受ける
契約前に「地中埋設物が出てきた場合の対応」について相手と確認しておきましょう。解体工事のように別途費用がかかると言うケースでも、事前に説明があるのとないのとでは心のありようもかなり変わってきます。
発見時は速やかに報告・記録
もし解体工事中に埋設物が出てきた場合には、速やかに写真付きで記録を取り、解体業者と協議します。この段階で地中埋設物に関して何の取り決めもない業者だと少し問題があるかもしれません。
撤去の必要性を判断
基本的には撤去することになります。例外的に建築に支障がなければ残すケースもありますが、売るにしても自分で活用するにしても、地中埋設物があって良いことは何もありませんので撤去することになります。
費用負担の範囲を確認
解体工事の場合は契約書や見積書に「地中埋設物の撤去費用は別途」と明記されるのが一般的です。不動産の売買契約書にも特例条項を盛り込んだりします。
地中埋設物の撤去費用相場
埋設物の種類や量、地域によって異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。
| 埋設物の種類 | 撤去費用相場(税別) |
|---|---|
| コンクリート | 10,000円前後~/㎥ |
| 地中梁・杭 | 7,000円~/本 |
| 浄化槽・便槽 | 50,000円〜150,000円/基 |
| 井戸の埋戻し | 100,000円~/個 |
| ガラ・生活ゴミ等 | 処分費+人件費 |
※見積り後に見つかった埋設物の場合は解体費用とは別に追加請求されるのが一般的です。
費用トラブルを防ぐためのポイント
- 契約時に「地中埋設物が出た場合」の条項を確認
- 口頭ではなく、書面で合意を残す
- 調査を依頼する
- 補助金制度(自治体による空き家解体補助など)を活用できる場合もあり
まとめ
地中埋設物は、解体後に初めて姿を現すことも多く、施主さんが覚えてない場合は費用やスケジュールへの影響が避けられません。ゆえに、事前確認と契約内容のチェックがトラブル回避のカギになります。
解体工事を安心して進めるために、信頼できる業者選びと、透明性のある見積・契約が大切です。