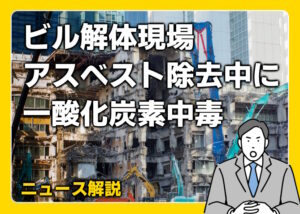解体工事トラブル全集【原因と対策】戸建て解体の注意ポイント

戸建て住宅の解体を検討している皆さまへ。
解体工事は「建物を壊すだけ」と思われがちですが、現代の解体工事は多くの準備と注意が必要な専門工事です。近隣住民との関係、法律の遵守、安全対策、そして環境への配慮まで、さまざまなポイントに気をつけなければ、施主様も解体業者も思わぬトラブルに巻き込まれてしまいます。
この記事では、実際に起こりがちな解体工事のトラブルとその原因、そして施主や解体業者が考慮すべき対策や予防策をわかりやすくご紹介します。解体工事を安心・安全に進めるために、ぜひ参考にしてください。
解体工事トラブル「近隣トラブル」
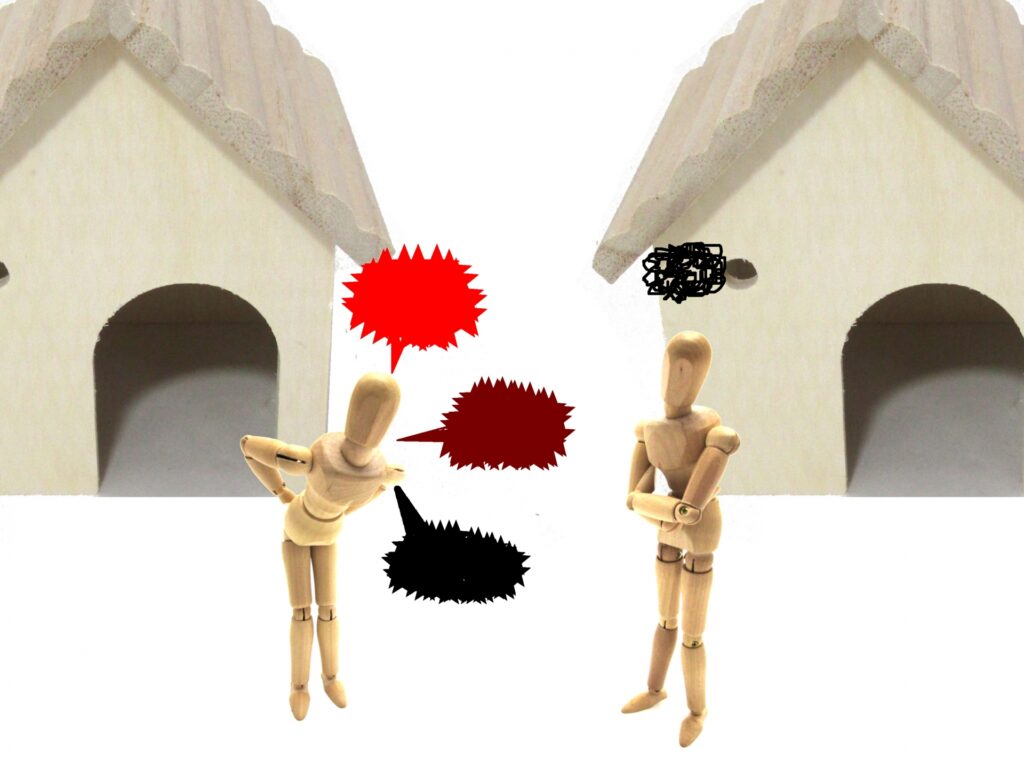
近隣への事前説明不足、防音・防塵対策の不備、不適切な作業時間(早朝・夜間)などが原因でご近所さんから苦情が出るケースがあります。
騒音や粉塵、振動に対するクレーム
建物を壊す解体工事ではどうしても大きな音や粉塵が発生します。また、重機による解体が始まるとお隣さんには振動が伝わるケースも珍しくありません。そのためご近所の方々から「うるさい」「ホコリがひどい」「振動で不安になる」などのクレームを頂戴することも。
対策・予防策
- 養生シートやパネルで解体現場を囲って粉塵や音を緩和する
- 低騒音型重機を使用する
- 騒音の大きな作業は日中に行い、早朝や夕方以降は控える
- 散水を行って粉塵を抑える
- アドリングストップの徹底
- 近隣住民への事前挨拶と説明で心づもりをしてもらう
お隣の家を損壊してしまった
あってはならないことですが、注意深く作業をしていても思わぬ不可抗力などでお隣の塀や外壁、植栽などを傷つけてしまうケースがあります。施主さんとしてできることはあまりありませんが、解体業者が賠償保険に加入しているかどうかのチェックはしておきたいところです。
対策・予防策
- 養生シートやパネルを設定して防護する
- 建物の構造を入念にチェックしておく
- 境界線を越えているものはチェックしておく
- 重機の旋回や動作範囲を制限する
- 境界付近の構造物は慎重に分離解体する
- ゴミやホコリが飛散しないようこまめに清掃する
- 万一のための賠償責任保険に加入する
路上駐車が迷惑
解体工事中は大型トラックや重機などが頻繁に出入りします。工事を迅速に終わらせるために仕方ないことですが、路上駐車などをして近隣住民の方や通行者に迷惑がかかるとクレームになります。そもそも停めない仕組み作りと一時的な対応力の確保が重要になります。
対策・予防策
- 敷地内や周辺で駐車可能な場所を確保しておく
- 管轄警察署に工事中の駐車許可をもらう
- 必要に応じて交通誘導員を配置する
- 近隣住民への説明時に不都合があった場合の連絡先を伝え早急な対応体制を敷いておく
- 工事車両に会社名や連絡先を明記した表示板を設置する
- アイドリングストップの徹底
- 路上駐車が避けられない場合は駐車時間を工夫する
ゴキブリやネズミが隣の家へ侵入
長年放置されていたような空き家の解体の場合、ゴキブリなどの害虫やネズミなどが居場所を追われて隣の家へ逃げ込む危険性があります。ネットの検索ワードでも「隣 解体工事 ゴキブリ」といったワードが表示されるくらいポピュラーな心配事ですのであらかじめ対策をしておいた方が良いでしょう。
対策・予防策
- 解体工事前に駆除業者に依頼して駆除する
- 解体工事前に市販の駆除剤を使って駆除する
- 隣接地の境界に殺虫剤や忌避剤をまく
- 隣家の通風口や隙間に工事期間中の目張りを依頼する
- 隣家に害虫駆除剤や忌避剤を提供する
- 苦情連絡先を周知しておく
解体工事トラブル「見積もりと請求額の乖離」

事前に知らされていた見積額と、実際に工事をした後の請求額が大きく違っていたというトラブルです。
追加費用の説明がなく請求時に突然上乗せされた
基本的に、解体工事は事前に現地調査をして見積りが出され、それに沿って工事が進められます。しかし、調査時には想定できなかった作業が発生してしまうケースもなくはありません。例えば地中に埋設物が発見されたような場合です。
対策・予防策
- 追加費用が発生しうるケースを業者と施主で書面で共有しておく
(地中埋設物、専門業者の外注費等) - 追加費用となりそうなケースは迅速に施主へ連絡する
- 施主の同意なしに追加作業は行わない
当然と思っていた工事がオプション扱いだった
例えば、解体後に土地の売却を考えているようなケースだと、解体するのは家屋だけではなく塀や植栽、カーポートなども含まれているはずです。しかし、施主がそのつもりでも、蓋を開けてみると解体対象は家屋のみで塀などは別途費用が必要だったというケースがあります。
対策・予防策
- 解体対象を具体的に確認し見積り書などに明文化しておく
(要注意項目)
✅土間コンクリートやブロック塀
✅庭木や庭石、倉庫
✅浄化槽や井戸など地中埋設物
✅アスベスト調査と除去
✅家具などの残置物の処分
✅整地の範囲 - 「見積り書」の"一式"表記の内訳があるか確認する
解体工事トラブル「書類や届出の不備」
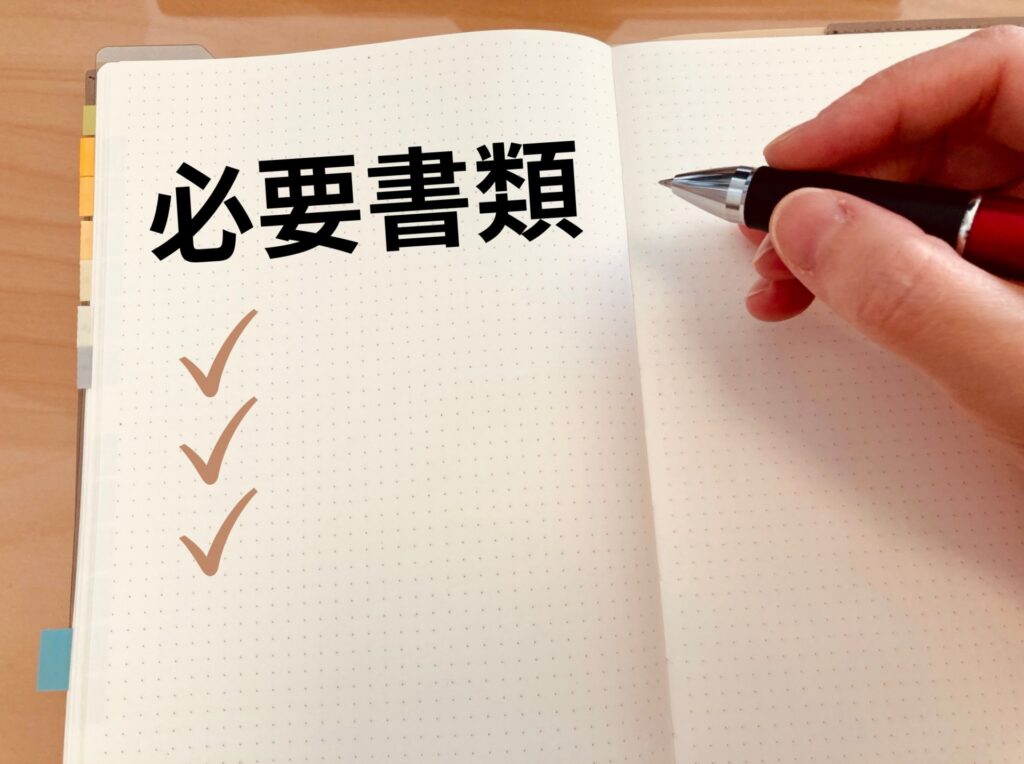
必要な書類がもらえなかったり、行政への届け出がされてないケースです。罰則や工事中止命令が出されることもあります。
建設リサイクル法の届出の未提出・遅延
建設リサイクル法では、延べ床面積80㎡以上の建物を解体する場合には届け出が必要です。怠ると着工の遅れや行政からの工事中止命令などの事態を招き、最大で20万円以下の過料を科されることもあります。
対策
- 延べ床面積80㎡以上か確認しておく
- 工事の7日前までに提出する
- 届け出先(建築指導課など)を確認しておく
- 控えの保管
アスベスト関連の調査・届出がされていない
アスベスト含有建材の事前調査および報告は2022年より義務化されています。怠ると最大20万円以下の過料や行政指導の対象になるばかりでなく、深刻な健康被害につながることもあります。
対策
- アスベストの事前調査について確認する
✅現在はすべての建物でアスベスト調査をしなければならない
✅調査は資格保有者が行う必要がある
✅着工前に行う - 調査報告書・届出済書類を確認する
道路使用許可・占用許可を取っていない
解体工事の足場や養生が道路にはみ出す場合は警察署への道路使用許可が必要です。許可を取らない場合、警察の介入で工事が中断されるリスクがあります。また、トラックなどを路駐していた場合には周辺住民とのトラブルに発展する可能性もあります。
対策
- 許可の必要性を事前に確認しておく
- 許可申請は早めに行う
- 周辺住民への告知をしておく
解体工事業登録のない業者が施工していた
解体工事を請け負うには解体工事業登録か建設業の許可が必要で、無許可の場合は違法行為となり罰則や指導対象となります。場合によっては施主が「業者選定責任」を問われるケースもあります。
👉岡山の解体工事業者一覧
対策
- 「解体工事業登録証」または「建設業許可証」の確認
※自治体のHPでも確認可能 - 有効期限の確認
- 施工実績の確認
- 安さだけでなく信頼性も重視する
マニフェスト(産業廃棄物管理票)の不備
解体工事で発生した廃棄物(解体ゴミ)は、マニフェスト制度に基づいて管理と報告が義務付けられています。正しく処理されてない場合は不法投棄や法令違反の責任が問われることになります。
対策
- マニフェスト対応かどうかの確認
- 「産業廃棄物収集運搬業」「「産業廃棄物処分業」の許可の確認
- 許可の有効期限の確認
- マニフェスト伝票の控えを保管
滅失登記の未提出
解体工事を終えた後は「滅失登記」を法務局へ提出しなければなりません。提出しないと登記上では建物があることになるので、土地売却時や相続・税金関連の手続きが進めらなくなります。
対策
- 滅失登記を行う人の確認
- 解体証明書の受け取り
解体工事トラブル「産廃の処理ミス・不法投棄」

解体で出た廃棄物は産業廃棄物に分類され、最終処分まで書面による管理が必須となっています。この管理がされておらず、不法投棄されていた場合、施主様もトラブルに巻き込まれる可能性があります。
廃棄物を不法投棄された
解体業者や産廃の運搬業者が、正規の処分場ではない山中や空き地などに廃棄物を不正に投棄して解体費を安く済ませる事案が毎年のように発生しています。既述の通り、これは違法行為であり、罰則が科されることになります。
対策
- マニフェスト対応かどうかの確認
- 「産業廃棄物収集運搬業」「「産業廃棄物処分業」の許可の確認
- 解体費の見積もりが相場よりもかなり安くないかチェック
- 委託契約書に中間処理・最終処分先が記載されているか確認
家具・家電を勝手に産廃扱いで処分された
解体時に家屋内に残されているものは残置物として扱われます。残置物は業者により処分されることが多いため、着工までに施主様が対応しておく必要があります。
対策
- 着工までに持ち出しておく
- 無理なら解体業者に処分しないよう伝える
解体工事トラブル「安全管理の不備」

万一、解体工事中の事故で死傷者が発生すると、工事が止まり、マスコミに報道されるような事態になります。解体後の土地の活用に大きな影を落とすことにもなりかねません。
足場や重機が倒れる
足場の固定ミスや強風対策が不十分で倒壊事故につながることがあります。労働安全衛生法違反や重大な労災事故につながる恐れがあります。
対策
- 主任者の元で手順通りに行われているか
- 強風時などに対応した補強ができているか
- 重機は有資格者が操作しているか
- 敷鉄板や枕木などで地盤補強しているか
- 点検作業はこまめに実施されているか
- KY活動で危険を共有できているか
作業員が負傷する
ヘルメットや安全帯など、作業員の安全装備が不十分だった場合にケガをしたり熱中症で倒れたりするケースがあります。
対策
- ヘルメットや安全帯などの安全装備は義務化できているか
- KY活動が実施できているか
- 初めての作業における手順確認と教育はできているか
- 休憩はきちんととれているか
- 作業員の体調管理が現場レベルでできているか
- 不安全行動を注意できているか
- 緊急時の連絡体制が周知されているか
火災やガス漏れ事故
解体前に電気・ガス・水道の解約をしてないと火災やガス漏れの事故につながります。特に古い家屋では要注意です。また、密閉空間で内燃式の発電装置を使うなどして作業員が一酸化中毒で搬送されたりといった事故が後を絶ちません。
対策
- 電気やガスなどの停止・解約ができているかの確認
- 電気配線やガス管の状況確認
- 火気厳禁区域の設定
- 内燃機器の使用ルールの徹底
- 異常発生時の対応周知
解体工事トラブル「悪徳業者による被害」

誤解や落ち度ではなく、最初から悪意を持ってお金をぼったくろうとする業者もいます。突然の連絡不通やずさんな工事で施主様の被害も甚大なものになるため要注意です。
悪徳業者によるトラブル例
- 工事費用を前払いさせ連絡普通になる
- 見積もり時よりも大幅に高額な請求をされる
- 施工がずさんで後からトラブルが発覚
- 許可や資格がない
- 産廃処分費を浮かせるために不法投棄
- 保険や補助金の虚偽申請をさせる
対策
✅ホームページや会社の所在地が明確か
✅過去の実績や口コミがあるか
✅名刺や請負契約書をきちんと用意してくれるか
✅建設業や解体業の許可を取っているか
✅前金一括払いではなく完工後払いになっているか
トラブルを防ぐために「確認」と「信頼」がカギ
解体工事にまつわるトラブルの多くは、「知らなかった」「確認していなかった」ことから始まります。依頼主として事前に知識を持ち、信頼できる業者を選び、しっかり話し合ってから契約することが何よりの予防策です。
本記事で紹介した内容は、実際に多くの現場で起きているトラブルをもとに構成されています。「うちは関係ない」と思わずに、一つひとつのポイントをチェックして、後悔のない解体工事を進めていきましょう。
手前味噌ですが・・・
日本クレストでは、こうした不安を感じるお客様にも安心していただけるよう、初回のご相談から見積もり、契約、工事中の報告、完了後の書類対応まで、すべての工程を丁寧にサポートいたします。
産業廃棄物中間処理場を自社で保有しており、解体ごみの処分費をかなり抑えられる体制を整えています。また、公共工事も多数手がけている実績とそれに基づく信頼があり、施工品質・安全管理にも万全を期しています。
工事の進捗状況はLINEなどを通じて随時ご報告し、近隣への挨拶や防塵・防音対策も徹底。はじめての解体工事でも「頼んでよかった」と思っていただける対応を心がけております。
しつこい営業などは一切いたしませんので、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。086-948-0001受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでお問い合わせ